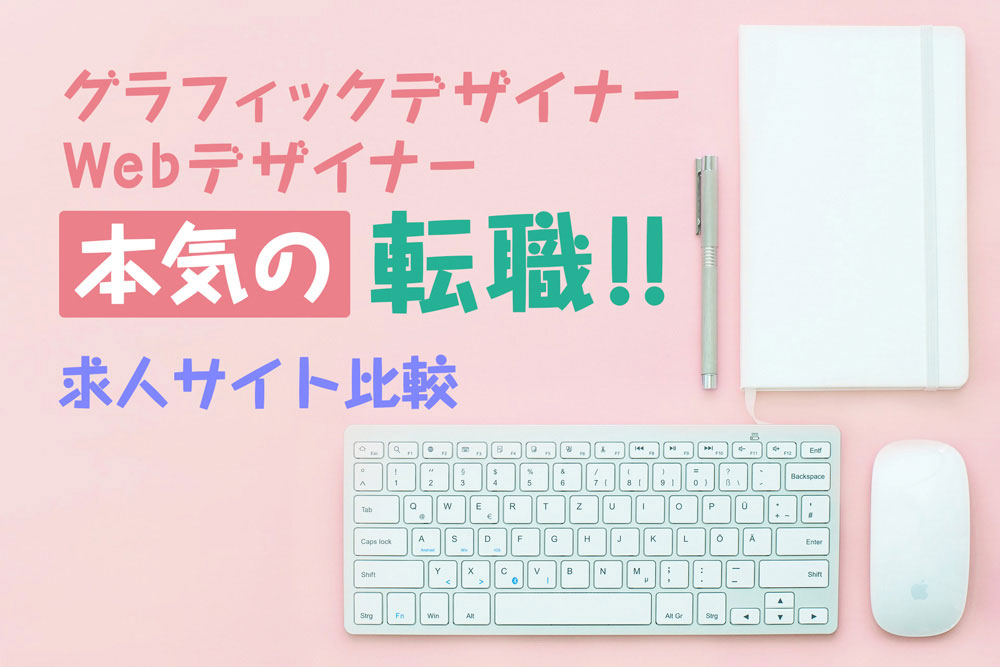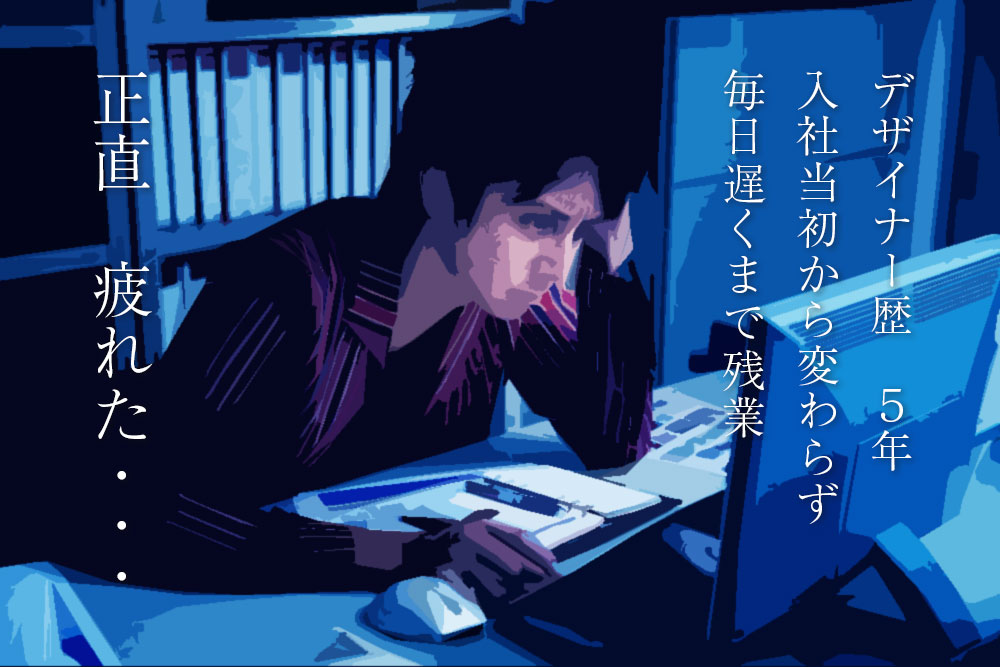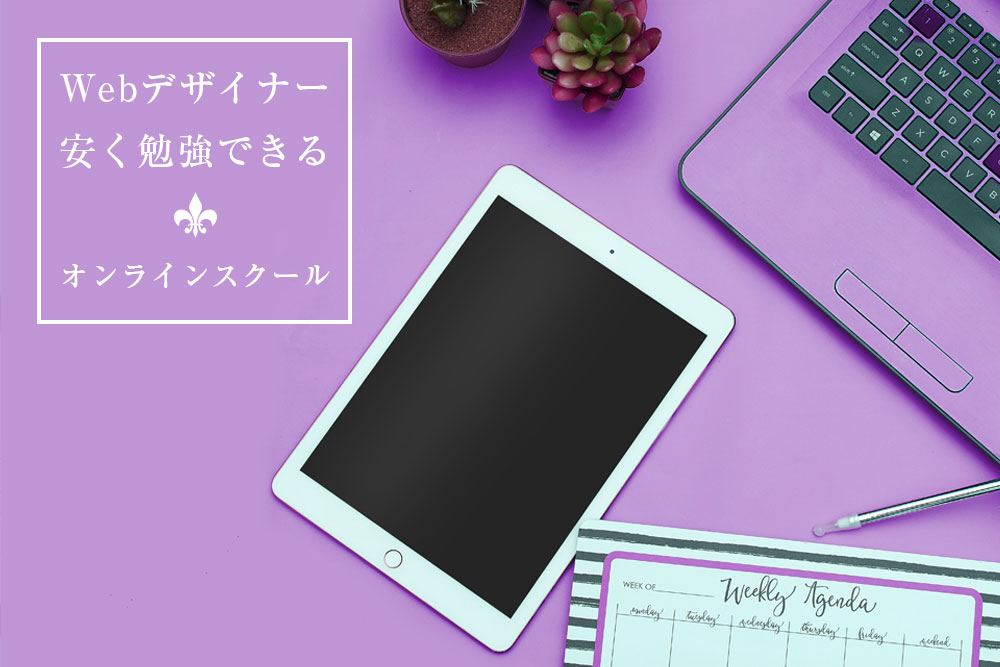デザイナーはパソコンに向かって、デザインを作るだけが仕事ではありません。
デザインスキルの他にも、以下の能力が重要になってきます。
- コミュニケーション能力
- ヒアリング力
- ディレクション能力
おもに対人スキルですね。
今回は、デザイナーがデザイン業務以外で必要な能力について紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
スポンサーリンク
内容がサクッと分かる目次
デザイナーがデザイン作業に入る前に大事なステップは、クライアントからの「ヒアリング」
クライアントへのヒアリングは、まず初めに大事なステップです。
具体的にどんなことをヒアリングしたら良いか、解説しますね。
ブランドイメージを固める
制作を依頼されたモノに関しては、必ずクライアントの方でブランドイメージを持っています。
ブランドイメージの他にも、
- ターゲット層
- イメージカラー
- 商品知識
- どういう販促ツールなのか
など様々あります。
時には、ブランドイメージが特にないもののデザインを依頼させることもあります。
良くも悪くも「丸投げ状態」でデザインを請け負わなければなりません。
例えば、美容系だったら女性らしいイメージで、IT系だったらスタイリッシュなイメージで、などシーンにあったデザインを提案してみしましょう。
競合他社のリサーチ
デザインの作業に入る前のヒアリングの段階で、競合他社のリサーチも事前に行っておく必要もあります。
クライアントが競合他社を教えてくれることも多いのですが、必ず自分の目でライバルのチェックは行っておきましょう。
特に、デザインの方向性が被らないための確認作業でもあるので、他社製品はどういったデザイン展開をしているのかなども調査しておくことが大切です。
デザインの方向性
ブランドイメージを共有することも大事ですが、作り上げていくデザインの方向性も必ず共有しておきましょう。
ここがズレてしまうと、デザイナー側が度重なる修正に対応しなければならないので、自分で自分の首を絞めてしまいます。
時に、デザインの方向性がブレブレなクライアントもいますが、デザインの方向性を決める手助けを必ず行なってくださいね。
スポンサーリンク
制作するものの完成イメージの方向性をクライアントと揃えておく
デザインの現場では往々に起こりえることなのですが、本格的なデザイン作業に入る前にデザインの方向性をクライアントと突き詰めて話しておかないと、後々面倒なことが起きてしまうことがあります。
終盤で大幅な変更くらったり、必要以上に修正を求められたり。。。
中には実際完成したものを見て、やっぱりイメージと違うから最初から。。。
という最悪なパターンもあります。
そういった事態を招かないためにも、クライアントとデザイナー間で共通のビジュアルイメージを作っておくと良いです。
例えば、既存である商品や広告を参照しても良いでしょう。
本格的なデザインに入る前に、デザイナーサイドでいくつかのラフイメージ案を提案して、クライアントに選んでもらっても良いでしょう。
また、クライアントの中には、口頭や参考資料だけだと頭の中でイメージが沸かず、出来たものを実際に目で確認しないと分からないという人もいます。
そのためにも、共通のビジュアルイメージを持つことはもちろん、デザインは都度、確認することも大切です。
事前にデザイン性を決め込んでいても、作業進行中に覆されることもある
共通のビジュアルイメージを持ってデザイン作業を進めていても、クライアントから最初に決めたデザインと大幅に変更したいと言われることもあります。
「よりいいものを作りたい。」
デザインは揉まれてこそ良いものが出来上がるとも言えるので、それは当然のこととも言えます。
しかし、我々デザイナーがその要望にすべて無償で答えていたら、まったく割に合わない仕事になってしまいます。
雇われや会社勤めのデザイナーの場合、その作業も給料に含まれていますが、業務委託・フリーランス・外注デザイナーは、その仕事につきっきりになってしまい、時間が拘束されてしまうことにより他の仕事が滞ってしまいます。
その場合、修正込みで最初から高めの金額設定で仕事を請け負うか、あとで別途追加料金を発生させるなど、柔軟な対応が必要です。
デザイン以外の業務上の取り決めも事前に行っておく
デザインを進める上での話とは少しズレますが、仕事を受ける前にはそう言った業務上の取り決めも事前に行っておく必要があります。
ちなみに私はフリーランスデビュー当初、修正回数を事前に決めていなかったので、修正を何度もくらったことがありました。
数回程度の修正なら良いのですが、あまりにも度がすぎる修正をもらうと、かなり割に合わなくなってしまいます。
(この場合の修正は、こちらのミスはもちろん除いています。)
良いモノを作るためには、修正作業も大切な行程ですが、
「修正が多すぎる!」
「え?最初決めたことからどんどんズレて来てるけど?」
と、作業を進めていくうちに腑に落ちない事も起きますが、相手はお客様なので、一概にすべて「できません」とは言えないものです。
だから、デザインの方向性以外にも、事前の取り決めが必要になってくるのです。
スポンサーリンク
ディレクション能力は必須。コミュニケーション能力があるとなお良し
デザインの最終決定権は、基本的にはクライアントにあります。
しかし「クライアントの言うことは絶対」なのでしょうか。
クライアントの好みですべてのデザインが決定してしまうと、デザイン性からかけ離れたいわゆる「ダサいデザイン」に仕上がってしまうことも往々にしてあります。
しかし、クライアントありきの仕事なので、我々デザイナーが下手に食い下がる訳にもいかないこともあります。
この辺はデザイナーが葛藤する場面。
誰がどう見てもダサいデザインが採用されることを良しとして良いのでしょうか。
完成デザインがどんなにダサくても、クライアントの言うことは絶対?
これは私が前に勤めていた社長の話です。
完成に近いデザインを社長に確認してもらおうと提出したところ、色の配色の指定や文字の大きさを1mm単位で指示されました。
その社長はデザインに関してはもちろん素人で、指示通りに仕上がったデザインは当然ダサい。
それでも社長は、自分のデザインに大満足したのでそのデザインが採用となりました。
これは私のディレクション能力の問題もあると思いますが、逆らおうものならものすごい形相でキレられたので、言い出すことはできませんでした(苦笑)。
デザインに限らず社内全体が社長の好みそうなものを提出する傾向にあり、私も例に漏れず、社長が好みそうなデザインを作っていました。
それがダサくても、自分の美意識に反するものでも、作っていました。
「デザイナーとしてこれでいいのかな」
ダサいデザインを量産する日々で、デザイナーとしてのスキルが鈍ってしまう感覚がしました。
そんなことを考えながら、日々の仕事をこなしていたを覚えてます。
デザイナーという仕事は、何かを作り上げていくクリエイティブな楽しみもある反面、自分が譲れない美意識のラインを、余裕で超えてくるクライアントの要望にも答えなければならない場面もあります。
だからデザイナーは、イラレ・フォトショを使ってデザインをするだけではなく、意見を取りまとめたり客観的な良し悪しをきちんとクライアントに伝えたりできる、ディレクション能力が必須なのです。
さらに言うならば、ディレクション能力に加え、いかにクライアントに上手く状況を説明できるかの、コミュニケーション能力も欠かせないスキルです。
仕事を獲得するうえでもコミュニケーション能力は外せませんしね。
パソコンでデザインをする以前に、仕事がもらえないと、せっかく持っているデザインスキルを発揮することができません。
フリーランスなら尚更大切な能力と言えるでしょう。
こちらもCHECK
-

人脈もコネもなし!!営業も苦手なフリーランスデザイナーが仕事を探す方法
続きを見る
人脈もコネもなし!!営業も苦手なフリーランスデザイナーが仕事を探す方法
まとめ
今回の記事の内容をまとめると、以下の通りです。
①事前ヒアリングをきちんとする
クライアントへのヒアリングは、まず初めに大事なステップ。
(内容:ブランドイメージ、ターゲット層、イメージカラー、どういう販促ツールなのか、商品知識、他社製品の調査など)
②クライアントと共通のビジュアルイメージを持つ
既存である商品や広告などの参考資料で共通の完成イメージを持つようにする。
こちらからデザインを提案する場合も、クライアントの意向を最大限に活かし、いくつかラフデザイン案を見せて方向性を確認しておく方がベター。
クライアントによってはイメージがわかない人もいるので注意。
そのためにも、デザインは都度、クライアントに確認を取る。
③良いデザインを作るためにはディレクション能力も不可欠
クライアントの言うことをすべて汲み取りながらデザインを完成させるのは至難の技。
必要なものと必要ではないものを明確にして、クライアントの意向を最大限に活かしながらデザインをより良い方向へ導くディレクター的役割も必要である。
ただパソコンに向かってデザインするだけがデザイナーの仕事ではありません。
このような対人スキルが必要になってくる場面も多くあるので、デザイナーは意外と大変なのです。